感性工学(秋山 正晴・感性AI株式会社)
企業側の思惑と消費者の感性は必ずしも一致するとは限りません。ただ、科学的手法を用いることで、消費者の「いいね」に近づくことができます。
手に取りたいパッケージ、質感のよい素材、居心地のよい空間など日々の生活においてふれるさまざまなものに感性を活かせるフィールドが広がっています。

講師プロフィール
1974年生まれ。1997年都市銀行に入行。都内店舗で窓口・融資業務を担当後、システム部門でダイレクトバンキング(インターネット・電話・モバイル)などの開発に従事。2005年京王電鉄に入社。経営企画部門(グループIT戦略、グループ事業計画立案、M&A)を経験。京王電鉄バスに出向後、高速貸切バス事業やMaaS(Mobility as a Service) 企画・推進などを担当。2022年6月より 感性AI株式会社 代表取締役社長CEOに就任。消費者の共感を得られるものづくりやマーケティングを目指す企業の支援を行う。趣味は温泉巡り。
科目概要
昨今の市場環境は変化が早く厳しい競争環境にさらされており、価格や機能だけは他社との差別化が難しい状況にあります。そのような中、商品やサービスの陳腐化や価格競争を避けるための新しい付加価値として感性に着目する企業が増えています。感性を客観的なデータとして取得・分析してビジネスに活かすこと、これが感性工学の根底です。
本プログラムでは、数学的な説明は極力行わず、ビジネスシーンでの活用事例に重点を置きながら、感性工学の概要について解説させていただきます。
オフィスアワー *有料会員限定
2025年1月22日(水)20:00~
ライブ
中川との対談!
2025年1月8日(水)20:00~
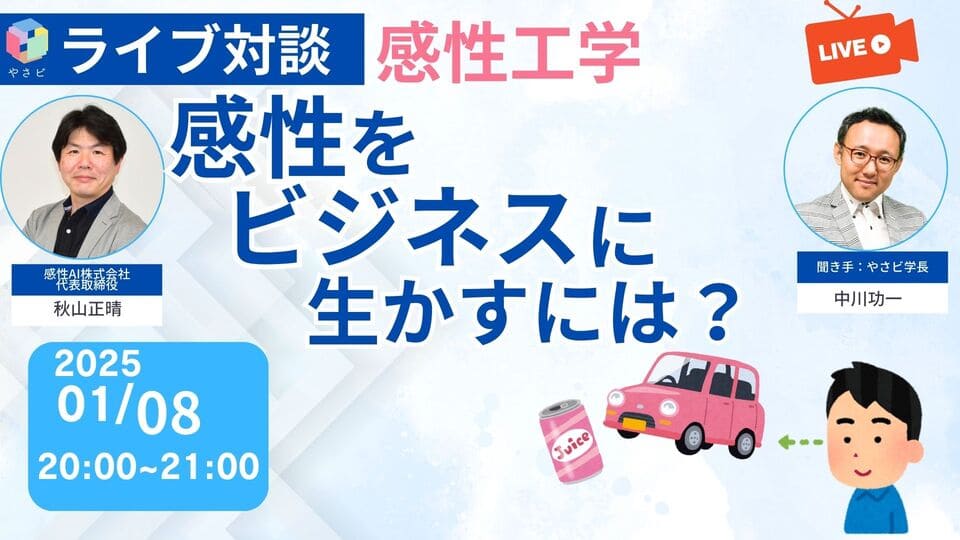
消費者の感性を知ろう~消費者行動は感性に左右されます~
今回は、「感性をビジネスに役立ててみませんか?」ということがテーマです。工学というと数学・物理をイメージして特に文系の方は「げっ!!」と思うかもしれませんが、今回は、感性という分野に興味を持ってもらうことを目的にしていますので、数式を使わず、分かりやすく全体像を説明したいと思っています。(私も文系です)
オンデマンド講義
第1回 イントロダクション
2025年1月6日(月)12:00~
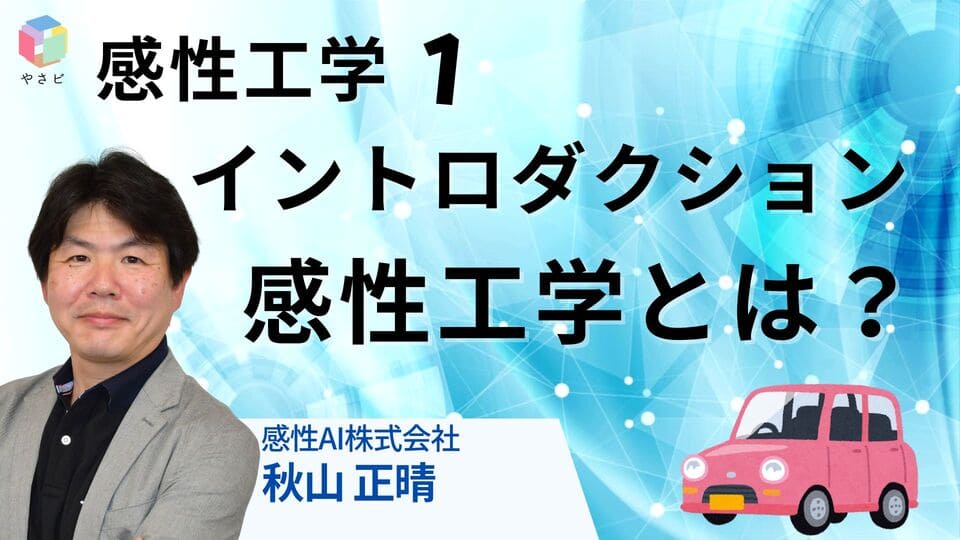
・授業計画の全容
・感性工学を学ぶ意義
・感性工学とは(定義,歴史(成立背景)、全体像)
第2回 感性とは
2025年1月8日(水)12:00~
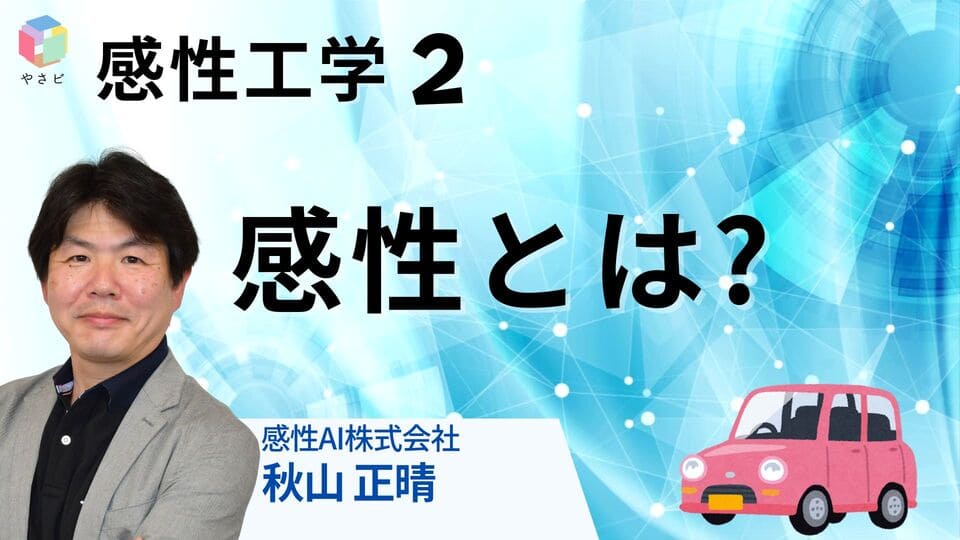
・感性の定義
・人間の情報処理のプロセス(知覚・認知・感情)
・五感の役割
・ゲシュタルト心理学
第3回 五感に着目しよう①(視覚)
2025年1月13日(月)12:00~
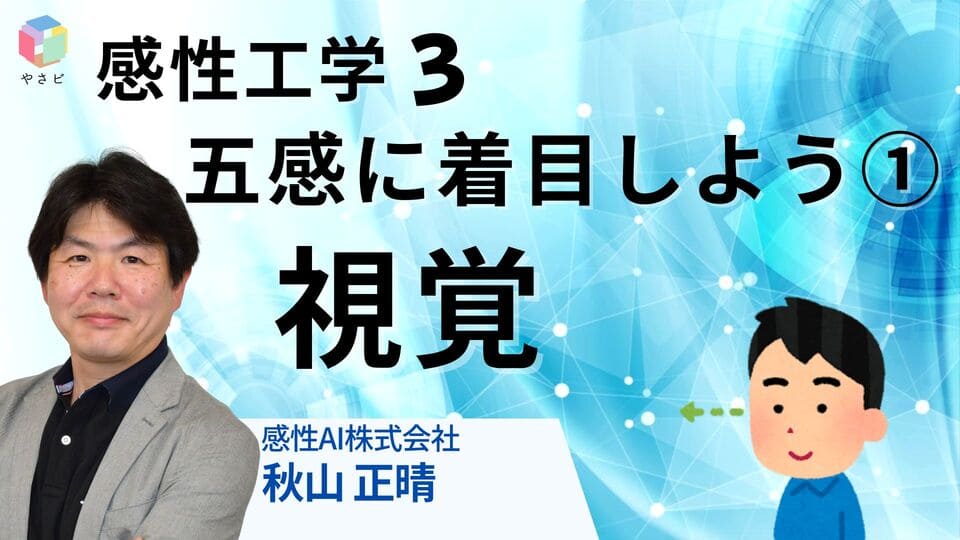
・光の物理的特性
・視覚の仕組み
・色の特性と感性
・視覚×感性の活用事例
第4回 五感に着目しよう②(聴覚)
2025年1月15日(水)12:00~
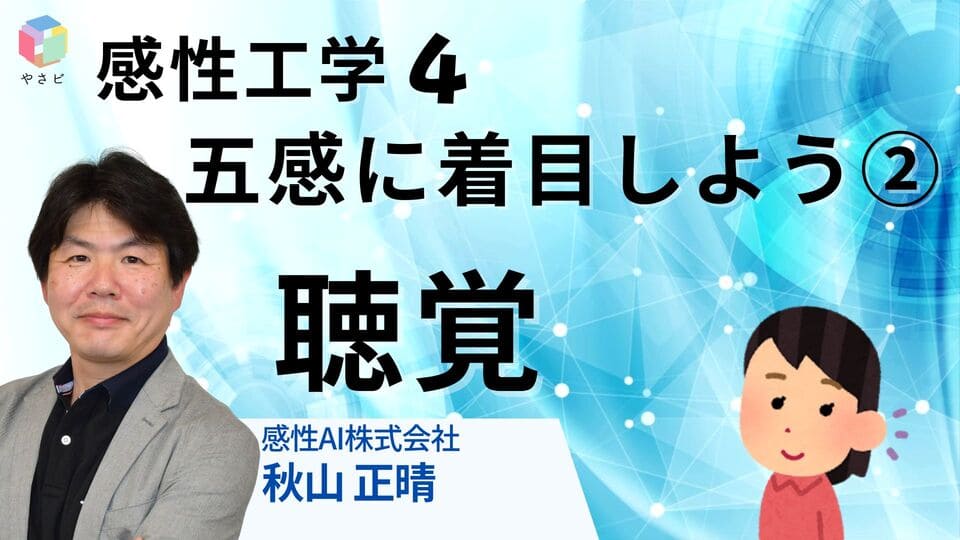
・音の特性 (周波数解析)
・聴覚の仕組み
・カクテルパーティー効果
・音韻と感性(ブーバ・キキ)
・聴覚×感性の活用事例
第5回 五感に着目しよう③(触覚・嗅覚・味覚)
2025年1月20日(月)12:00~
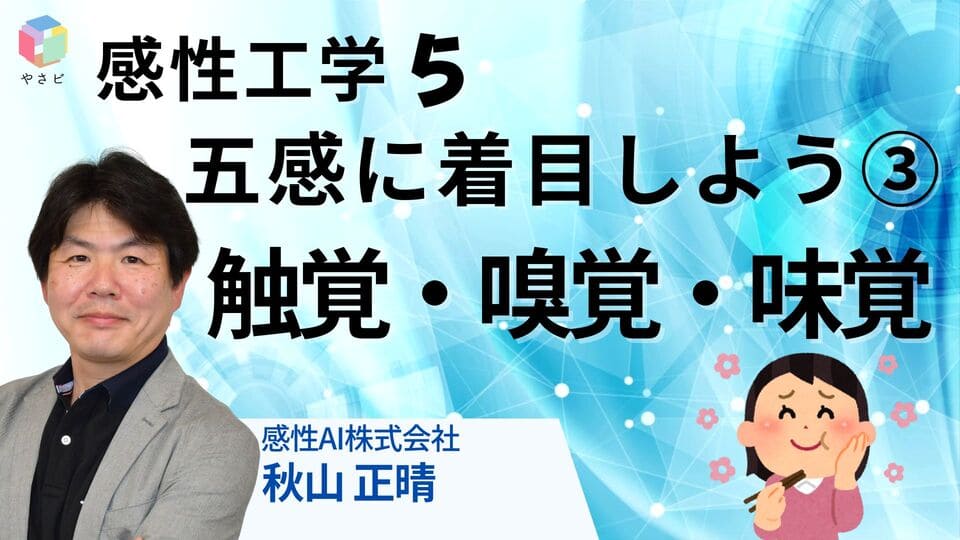
(1)触覚
・触覚の仕組み
・触覚の発展形:熱さ、痛み、かゆみ
・触感の再現(最新の技術)
・触覚×感性の活用事例
(2)嗅覚
・においの特性
・嗅覚の仕組み
・嗅覚×感性の活用事例
(3)味覚
・味の特性
・味覚の仕組み
・味覚×感性の活用事例
第6回 感性を把握しよう① ~感性の測定と分析~
2025年1月22日(水)12:00~
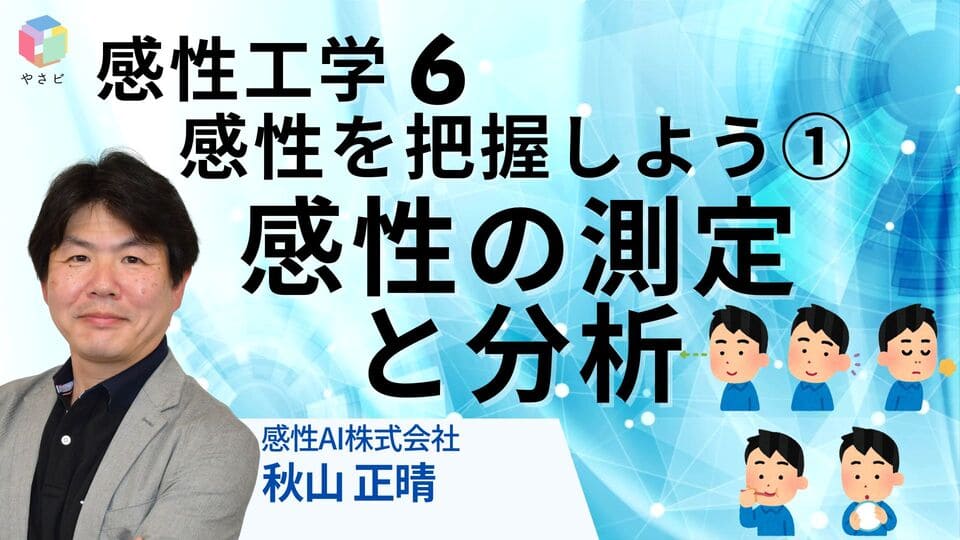
・感性可視化のスキーム(全体像)
・感性の測定方法
・感性データの分析方法
・分析のイメージ
第7回 感性を把握しよう② ~一連の流れをつかむ~
2025年1月27日(月)12:00~
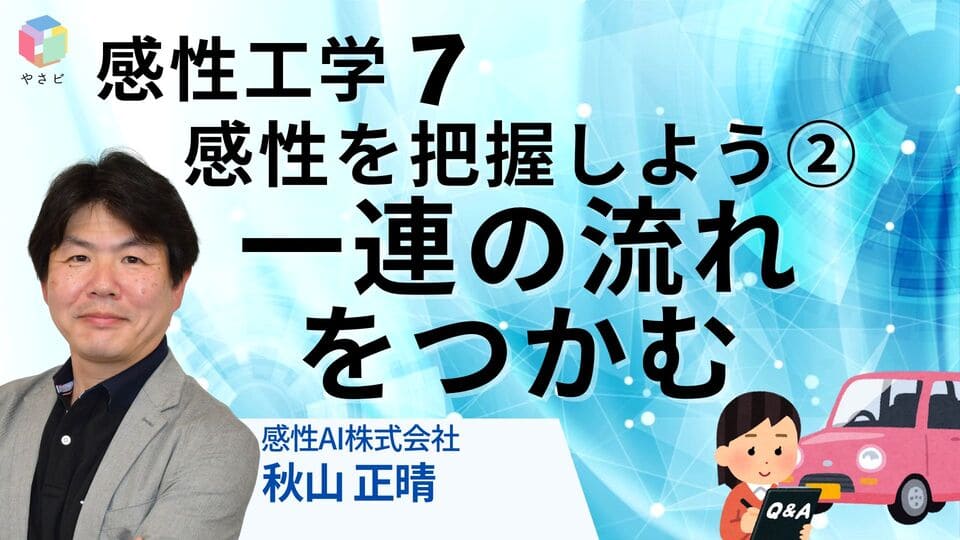
・実施プロセス
・コンセプト・テーマの設定
・感応評価・感性評価
・分析⇒対応⇒評価
第8回 感性を活用しよう
2025年1月29日(水)12:00~
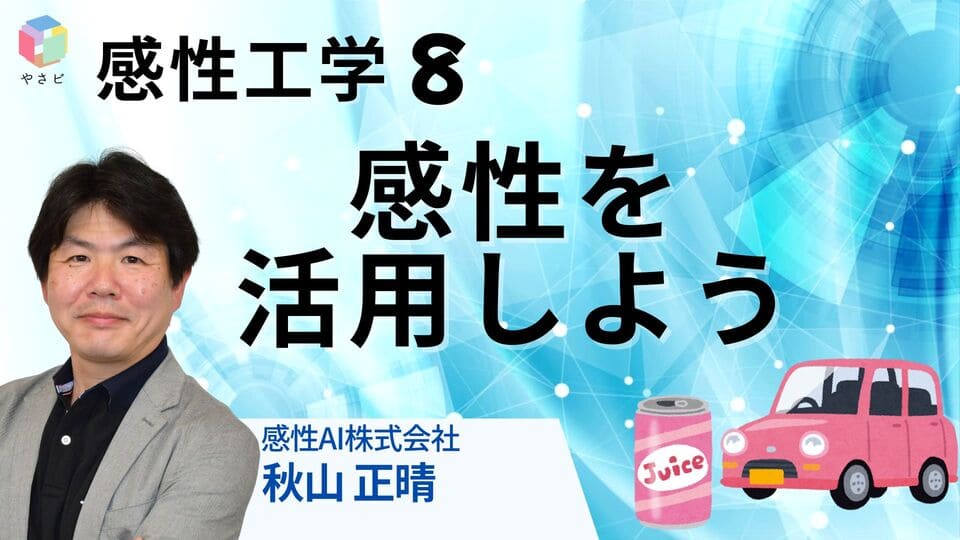
・感性に訴えかける商品開発
・感性を活用したマーケティング
さらなるアウトプットをしたい方へ
アドバンスドなチャレンジをしたい方向けに、特別な問題を用意しています。
学長からフィードバックいたしますので、ぜひ挑戦してみてください。
あわせて学長との面談を活用して、疑問質問など追加の質問もしてみてください!
アドバンスト問題はこちら
感性工学をもっと楽しむ!3つの企画
やさしいビジネススクール会員のみなさま、こんにちは!
やさしいビジネススクール「学習コンシェルジュ」です。
今回は「感性工学」をより深く、そして楽しく学ぶための新企画を3つご用意しました。
- ワークショップ:会員同士でワイワイ学び合う
- オフィスアワー:秋山先生を囲んで、気になることを直接質問
- アドバンスト問題サークル:統計や応用課題に挑戦し、みんなで理解を深める
いずれも「他の受講生との交流を増やしたい」「ライブ講義やオンデマンド講義を日常に活かしたい」という声から生まれた企画です。どれもノー準備・途中参加OKなので、お気軽にご参加ください。3つすべて参加すれば相乗効果も期待できるはずです!
下記にて各イベントの詳細と参加メリットをまとめていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
Zoom情報(3企画共通)
- 会員限定でお知らせしております!
① ワークショップ
感性工学の学びをもっと深め、仲間と楽しく交流しながら実生活や仕事に活かせるヒントを得ませんか?
やさビには、会員同士で自由に意見を交わし合い、知識をシェアしながらお互いに応援し合う温かなコミュニティがあります。ワークショップを通して学びを深めましょう!
今回はさらに、オンライン会議で使える“ちょっとした”アイスブレイクの方法も実践的に学べるので、日々のミーティングの質向上にもつながります。
初参加の方や準備が難しい方も大歓迎!
気軽に参加して、感性工学の魅力を思い切り楽しんでいきましょう。
日時
1/21(火) 20:00~21:00
こんな方におすすめ
- 感性工学をひと通り学んだけれど、より交流して理解を深めたい
- ライブ講義やオンデマンド講義をまだ見ていないけれど、まずは雰囲気をつかみたい
- 人と話しながら学ぶほうが楽しくてモチベーションが上がる
当日の流れ
- めっちゃ楽しいアイスブレイク(学修コンシェルジュ・山下)
- ライブ講義の簡単な振り返り(山下)
- 個別ワーク:「感性工学で気になること・秋山先生に聴いてみたいこと」をアウトプット
- ノー準備大歓迎! 事前にライブ講義・オンデマンド講義をチェックしておくとより深まります。
- グループワーク(ブレイクアウトルームにて交流予定)
- 進行:学習コンシェルジュ(山下) & ファシリテーター 西尾陽介 さん
- まとめ(次回企画のご案内など)
② オフィスアワー
前日のワークショップに参加した方は、そこで出た疑問をさらに深掘りできる場にもなります。もちろん、オフィスアワーからの参加でも大歓迎です!
日時
1/22(水) 20:00~21:00
こんな方におすすめ
- 秋山先生に直接質問してみたい、学びを深堀りしたい
- アドバンスト問題の進め方や具体事例が知りたい
- 感性工学を実務に活かすためのアドバイスを受けたい
当日の想定トピック
- 秋山先生へのQ&Aとディスカッション
- 感性工学の個別具体的な応用例
- アドバンスト問題に取り組むポイント
- 感性AI株式会社の取り組みや今後の展望
③ アドバンスト問題サークル
日時
2/5(水) 20:00~21:00
こんな方におすすめ
- アドバンスト問題をやろうと思うが、ひとりではなかなか進まない
- 課題の難しい部分や統計の考え方を一緒に学びたい
- 他の受講生との繋がりを持ちながら、確実に提出までたどり着きたい
サークル主宰
経営マスターゴールド 西尾陽介さん
サークル活動内容
- オンラインで1時間集まり、情報交換しながら課題に取り組む。
- 実際に入力や演習をしながら、その場で疑問点を共有。
- 完成に向けてお互いサポートし合うので、モチベーションも持続。
- エクセルシートで実際にワークします!
- 秋山先生より提供いただいた課題用エクセルを使って、手を動かしながら理解を深めます。
- 統計や分析要素が入っているので、一緒にやればわからないところも質問しやすい!
- 課題の理解が深まり、スムーズな提出につながります。また、仲間と学ぶことでペースメーカーができる点も大きい魅力です!
参考テキスト
【概略】今回の講義内容に沿って全体をもう一歩掘り下げたい
「感性工学への招待」篠原昭・清水義雄・坂本博 森北出版 →絶版 (図書館などで確認してください)
【理論】オノマトペをはじめとした心理学的手法を中心に概念・理論を深掘りしたい
「感性情報学」 坂本真樹 コロナ社 (2,600円+税)
【事例・手法】感性工学の活用事例と手法を徹底的に網羅したい
「感性工学ハンドブック~感性をきわめる七つ道具~」 椎塚久雄 朝倉書店 (16,000円+別)
【実践】実際にやってみたい、アンケートの取得と統計的な分析手法の具体的な中身を知りたい
「人間工学ガイド – 感性を科学する方法」 福田忠彦研究室 サイエンティスト社 (3,300円+税)