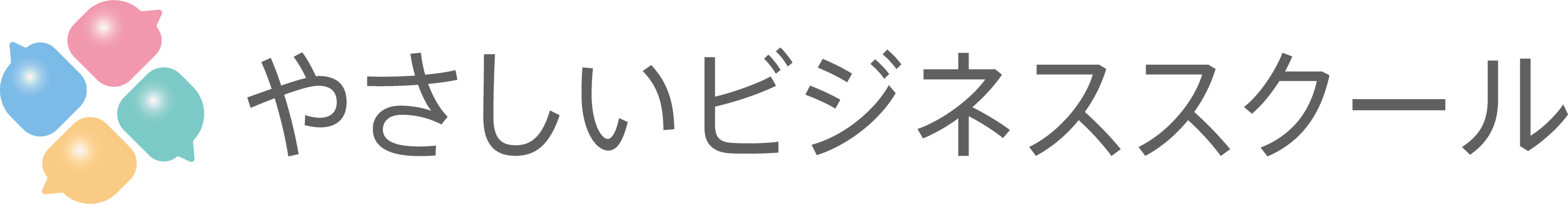マーケティングコンサルティング(中川功一・やさしいビジネススクール学長)

講師プロフィール
専門は経営戦略論、イノベーション・マネジメント。駒澤大学、大阪大学を経てやさしいビジネススクール設立。「アカデミーの力を社会に」を人生のライフワークに据える。国内外トップ誌に論文を掲載させつつ、コンサルタント、リサーチャー、研修や講義を通じて産業界の活性化を支援する。YouTubeでも実践の場に活きる経営学を発信している。
科目概要
クライアントの状況分析を行い、基本的な提案をするための基本技術&共通言語として、3C分析及びSTARを軸とした提案技法を習得します。クリエイティブやデザインの詳細には踏み込まず、ファクトに基づいた基礎的な分析能力と提案能力を磨く講座です。
オンデマンド講義
Part. 1 コンサルティング提案の基本
1-1 提案の基本形式STAR

コンサルティング提案の“王道フォーマット”が、このSTARです。
現状(Situation)から未来像(Target)を描き、具体的な行動(Action)と成果(Result)へ導く——ただの型ではなく、相手と共通理解を築きながら説得力を高める実践的な手法です。
ヤマト運輸の改革事例を通して「STARで組織を動かす」実際の姿を学び、コンサルとしての第一歩を踏み出しましょう。
1-2 基礎インプット、3C分析
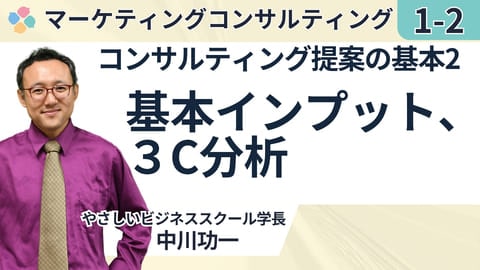
提案の精度は“3C分析”から始まります。
自社(Company)、競合(Competitor)、顧客(Customer)を徹底的に見極めることで、STARの土台が築かれます。
大塚製薬「ポカリスエット」の事例が示すように、3Cを外さないことが差別化と成功のカギ。
提案を通すための“勝てる戦略”は、まずこの3Cから生まれるのです。
1-3 アウトプットの基本形式
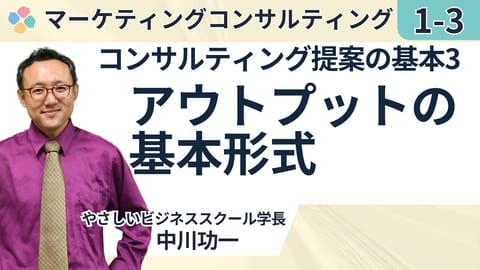
この回では、コンサルティング提案に欠かせない「アウトプットの型」を徹底解説します。
収益モデルをどう描くか(差別化・コスト・ニッチ・ビジネスモデル変革)、そこからSTPで市場を絞り込み、最終的に4Pに落とし込む——提案の王道プロセスを実例とともに学べます。
ウマミバーガーの日本進出戦略を題材に、差別化や高級路線の設計をシミュレーション。さらに、クライアントが動かせる変数を見極める視点や「リソースベースドビュー」に基づく戦略発想の重要性も伝えます。
マーケティング提案を“形”から“勝てる戦略”へと引き上げる、実践的なフレームワークを身につけましょう。
Part. 2 Company分析
2-1 事業ドメインとパーパス

ドメイン×パーパスで、提案のズレをゼロに。
本講義は「誰に・何を・どのように・なぜ」でビジネスを定義し、3C(誰に=Customer/何を=Company/どのように=Competitor)とWHYで核を固めます。
RBV(リソース基盤)とゴールデン・サークルを用い、ユニクロにアルマーニを勧めるような“ミス提案”を回避。
クライアントの存在意義に沿って課題を解く、納得と実行を生む戦略骨子とヒアリングの型が手に入ります。
明日から「WHYから始める」コンサルへアップデートしましょう。
2-2 ビジネスモデルキャンバス

事業を一枚で整理できる最強ツール、それがビジネスモデルキャンバスです。
価値提案・顧客・チャネル・収益・コストを順序立てて描けば、新規事業も既存分析も抜け漏れなく設計可能。
パン屋の事例を通じて、数字とビジョンをつなぐ実践的な使い方を学びます。
「事業の全体像を一目で掴む力」を、この講義で確実に身につけましょう。
2-3 バリューチェーン分析と7S

この回では、企業の「内側」を深く読み解くための2大フレームワークを学びます。
マッキンゼーが開発した 7S分析 で、戦略・組織構造・システム・人材・スキル・価値観・スタイルを徹底チェック。企業を“人間ドック”のように診断し、強みと課題を浮き彫りにします。
さらに、マイケル・ポーターの バリューチェーン分析 を用い、調達から販売・アフターサービスまでの一連の流れを分解。どこで価値が生まれ、どこに改善余地があるのかを明らかにします。
経営者の視点で「未来の強みをどう作るか」を考えるこの分析は、提案を一段と説得力あるものへと引き上げます。
Part. 3 Competitor分析
3-1 競合分析の基本

この講義では「競合分析」を扱います。ポイントは特別な手法があるわけではなく、自社分析に使ったフレームワークをそのまま競合に適用すること。ドメインやパーパス、ビジネスモデルキャンバス、バリューチェーン、7S分析を用いて、自社との違いを浮き彫りにします。
重要なのは「相手の社長の目線」に立つこと。トヨタから見た日産ではなく、日産の経営者として自社をどう見ているかを想像することで、真の強みや弱みが見えてきます。
アウトプットの基本は比較表や二軸図。シンプルながら、違いを一目で示すことで「なるほど」と納得を引き出せます。分析から違いを鮮やかに描き、提案へとつなげる——それが競合分析の技術です。
3-2 自社と競合の本質的違い

競合分析で重要なのは、単なる比較表や二軸図にとどまらず、企業の「本質的な強み」を掴むことです。
アマゾンの成長戦略やガリバーの在庫戦略、スターバックスの直営方式のように、部分的な分析では見えない“核”をどう描くかが問われます
そのためには、フレームワーク(バリューチェーン、ビジネスモデルキャンバス、7Sなど)を活用しつつ、繰り返し図解やデザインワークを行い、試行錯誤を通じて「これがこの会社の本質だ」と表現する力を養う必要があります。
競合を分析することは、クライアントの立ち位置を浮かび上がらせ、最適な戦略提案へとつなげるための実践的エクササイズです。
3-3 相手の出方を知る

この講義では「競合分析」を扱います。重要なのは、特別な手法を使うことではなく、自社分析に用いたフレームワークをそのまま競合に適用し、違いを浮き彫りにすることです。
大切なのは「相手の経営者の視点」に立つこと。外から眺めるのではなく、相手の立場で自社をどう捉えているかを想像することで、本当の強みや弱みが見えてきます。
アウトプットは比較表や二軸図といったシンプルな形で十分。違いを直感的に示し、納得感のある提案につなげていく——それが競合分析の技術です。
Part. 4 Customer分析
4-1 STP

この講義では、顧客を的確に捉えるための基本フレームワーク「STP(Segmentation・Targeting・Positioning)」を扱います。
市場をどう切り分けるか、どの層を狙うか、そしてその中で自社をどう位置づけるか——この3段階を踏むことで、戦略の精度は格段に高まります。
顧客を外せば、どんなに魅力的な広告や商品も響かない。逆に、ターゲットが鮮明に見えていれば、訴求の一言が市場を大きく動かすこともあります。
成功と失敗の差を決めるのは「誰に・どう売るか」。徹底したSTPこそが、マーケティング提案を機能させる鍵です。
4-2 ペルソナとカスタマージャーニーマップ
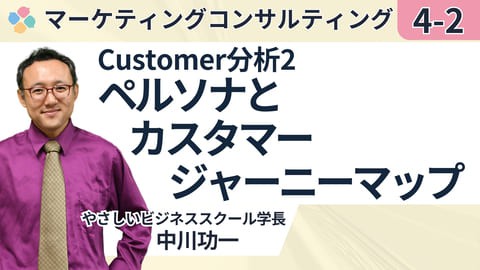
この講義では、STPから4Pへと戦略をつなぐカギとなる「ペルソナ分析」と「カスタマージャーニーマップ」を扱います。
顧客像を具体的に描き出すことで、価格・商品・販路・プロモーションが鮮明に見えてくる。さらに、購入に至るまでの心の動きを地図に落とすことで、どこに課題があるかを明らかにできます。
提案の精度を高め、顧客体験をデザインする力——それがこの2つの手法です。
4-3 消費者心理

この講義では「顧客心理」と「消費者行動」を扱います。
プロモーションは不要な商品を売りつける活動ではなく、本当に必要としている人に価値を理解してもらい、正しい価格で納得してもらう営みです。
顧客は「知る」から始まり、「興味を持ち」「欲しいと思い」「行動する」という心理の旅を進みます。その背後にあるのがAIDAモデルであり、カスタマージャーニーの基盤です。どの段階に働きかけるのかを理解すれば、広告や施策の目的も明確になります。
さらに重要なのは、顧客を「不思議な存在」としてではなく、一人の人間として捉えること。倫理を欠いた誘導ではなく、人との自然な関係性を築くことこそが、現代の顧客コミュニケーションに求められる姿勢です。
顧客心理を正しく理解することで、より誠実で効果的なマーケティング提案ができるようになります。
Part. 5 総合分析と提案
5-1 SWOT分析
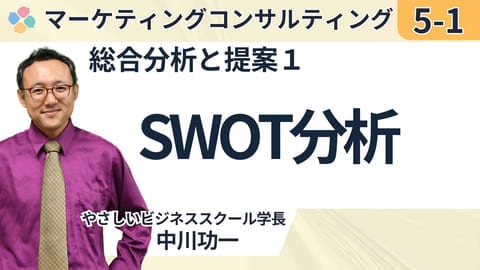
SWOT分析は、戦略立案の「原点」とも言える基本フレームワークです。
内部の強み・弱み、外部の機会・脅威を整理することで、複雑な情報をシンプルに俯瞰でき、戦略の焦点=「センターピン」を見極める力が磨かれます。
本講義では、実際の事例を素材に、情報をSWOTに落とし込み、どこに戦略的な焦点を置くべきかを考える演習を行います。
数ある分析の最後に、改めてSWOTに立ち返ることで、説得力ある提案の軸を築けるようになります。
5-2 クロスSWOT
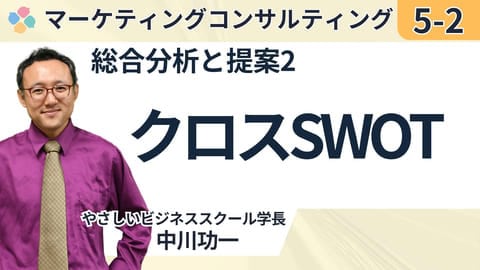
SWOT分析をさらに発展させ、強み・弱み・機会・脅威を“掛け合わせる”ことで突破口を見出すのが「クロスSWOT」です。
シンプルな整理だけでは見えない戦略の糸口を、要素同士の組み合わせから導き出す発想法。
本講義では、豊富な情報をどうつなぎ合わせれば「センターピン」となる焦点を発見できるのかを実践的に学びます。
直感やセンスに頼らず、発想を体系化するための思考トレーニングとしても効果的な手法です。
5-3 エコシステム戦略
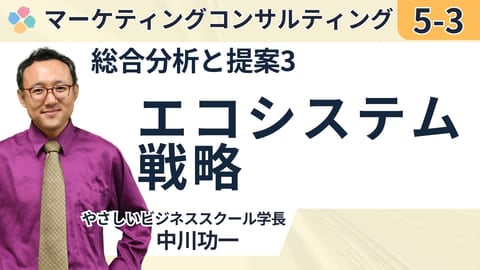
戦略を描くだけでは提案は不十分です。企業戦略を顧客体験(UX)に落とし込み、さらに複数の企業をつなぐ「エコシステム」として提案することが、今のコンサルタントに求められます。
本講義では、SWOT分析やクロスSWOTで導いた方向性をUXへと裏返し、顧客に届く体験価値へ転換する方法を学びます。さらに、デジタル化やDXが進む環境で重要性を増す「エコシステム戦略」を扱い、単なる部分最適ではなく全体を設計する発想を身につけます
これにより、単体の改善ではなく“総合的な体験を描き出し提案できる人材”へと成長することができます。提案を「勝てる戦略」へと仕上げる力を、最後の講義で習得してください。