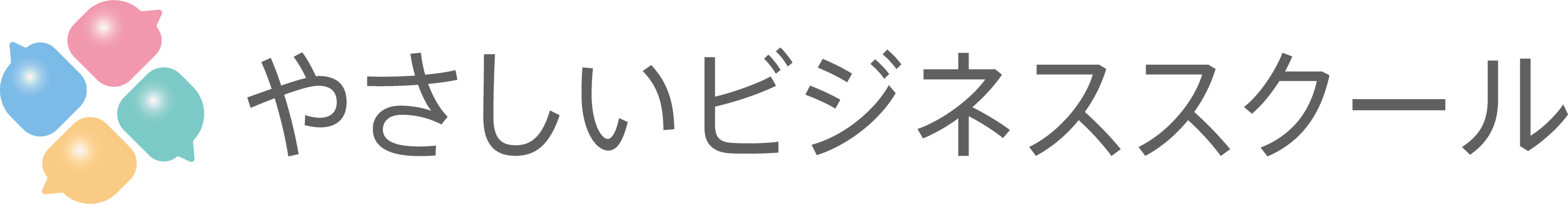【ゼミ】ワークショップ形式で考える 経済学・経営学(樋口 広喜・やさしいビジネス総研 研究員)
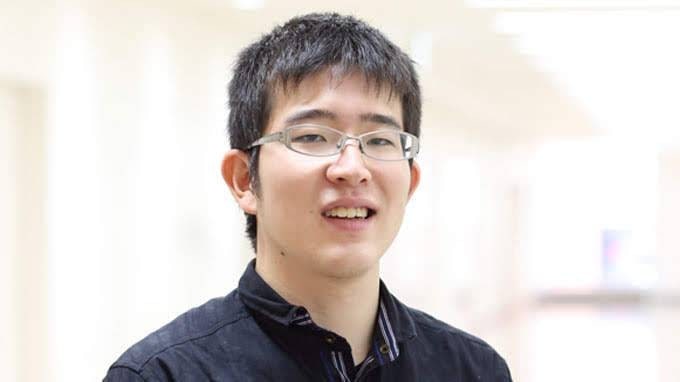
講師プロフィール
やさしいビジネス総研 研究員
2021年近畿大学経済学研究科修士課程修了。その後、民間企業勤務を経て、2024年より現職。
2023年より、近畿大学経営学部中村文亮講師、中川功一学長と「若者のSNS利用と消費行動に関する調査」に関する研究に携わる。
主な研究テーマは「若者の行動心理分析」
ゼミ概要
ワークショップ形式で考える経済・経営学
行動経済学シリーズ ~仕事にも日常にも使える心理トリック~
普段、何気なくしている判断や行動に、実は心理的な仕掛けが隠れているかもしれません!
このシリーズでは、仕事の悩みや日常の選択に役立つ行動経済学の理論を、みんなで楽しく議論しながら学んでいきます。仕事でもプライベートでも使える知識を、受講生同士の交流も兼ねつつ、リラックスした雰囲気で一緒に考えてみましょう。(月1・ZOOM開催・各回60分)*有料会員限定
ゼミ *有料会員限定
第1回:やめるのがもったいない?それともただの執着?(サンクコスト効果)
10/29(火) 20:00~
「ここまで頑張ったのに、途中でやめるのはもったいない…」そんな風に感じたこと、ありませんか?仕事でも趣味でも、一度始めたことをやめるタイミングって難しいですよね。サンクコスト効果を通じて、やめるか続けるかの悩みをみんなで議論しましょう!
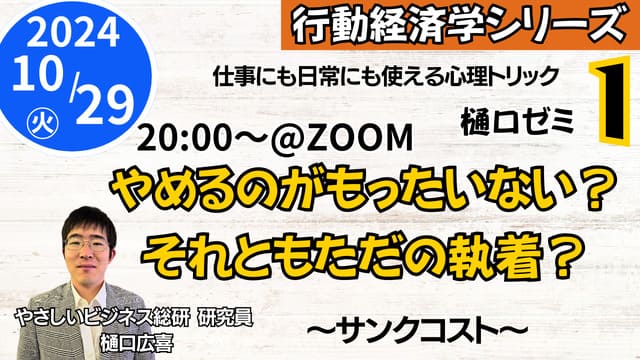
第2回:あなたに貼られた「ラベル」、それ本当に必要?(ラベリング効果)*準備中
11/26(火)20:00~
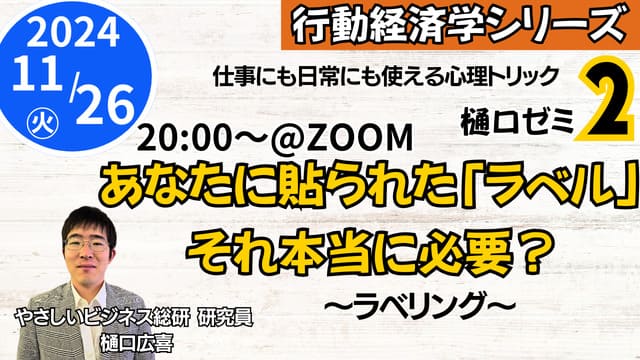
第2回 樋口ゼミ:行動経済学シリーズ
今回のテーマはラベリングです!
✓人は無意識にラベリングする生き物??
私たちは日常生活や仕事の中で、無意識に他人や自分にラベルを貼ることがよくあります。「仕事ができない人だ」「協調性がない」といった否定的なラベルもあれば、
「提案書作りが上手」「細かい所まで気が付く人」といった前向きなラベルもあります。
これらのラベルが、自分自身や他者の行動にどのような影響を与えているか、改めて考えてみませんか?
また、ラベルを上手に活用することで、成長を促すことも可能です。例えば、部下に「君はとても観察力がある」と伝えることで、その部下もそのラベルに応えようとするかもしれません。ラベリングには、こうした成長を後押しする面と、制約を与える面があると考えられます。
みなさんと考えてみたいこと
「ラベリングで意識したこと」「ラベリングされたこと」はありますか?
ラベリングは実際に行動にどのような影響を与えると感じますか?
✓ラベリングとマーケティングの関係
ラベリングはマーケティングにも多く利用されています。「○○女子」「××男子」といった表現で消費者にラベルを貼り、購買意欲を刺激する方法や、「あなただけの特別なサービス」「数量限定品」といった演出で購買行動を促すことがよく見られます。
しかし、こうしたマーケティングには、実際の内容と異なる特別感や希少性を演出してしまうリスクもあります。
ラベリングを効果的に、そして慎重に活用するにはどうすべきか、皆さんと一緒に考えたいと思います。
✓「闇バイト」にも潜む3つのラベリングの力
近年注目される「闇バイト」にもラベリングが影響を与えています。本来は犯罪行為であるにもかかわらず、「バイト」という名称が使われることで、罪悪感が薄められているのかもしれません。また、「履歴書不要」「あなただけの特別な仕事」といった求人のラべリングで誘われ、若者が巻き込まれてしまうケースも増えています。
さらに、一度関わった若者が軽犯罪から重罪にエスカレートする過程で、個人情報を抜き取られ「あなたはもう犯罪者で後戻りできない」というラベルを貼られることも後戻りを難しくしている要因なのかもしれません。ラベリングの「負の側面」が人の行動に与える影響についても、時間があれば、考察してみたいと思います。
第3回:その決断、本当に自分で決めてる?(プロスペクト理論)
12/26(木)20:00~
価格やリスクの判断を、直感で決めてしまうこと、よくありますよね。プロスペクト理論を使って、どうしてそんな決断をしてしまうのかをひも解き、仕事や日常での意思決定にどう活かせるかをみんなで話し合います。
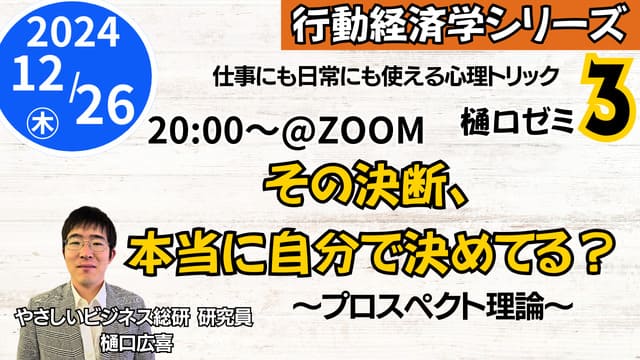
第3回 樋口ゼミ 行動経済学シリーズ
テーマ:「プロスペクト理論」
プロスペクト理論って言うと難しそうに聞こえますが、今回は特に「参照点」に注目して、日常生活での「損した」「得した」という感覚がどこから来るのかを一緒に考えてみたいと思います。
昨年話題になった北海道奈井江町の「クマ退治」。日給8500円って安すぎない?という声があがりました。「クマ退治」という危険な仕事には、もっと高い報酬が普通だと思っているからこそ「安い!」と感じるわけです。(一方でボランティアの延長と思えば、8500円も決して安くないとも言えそうですが)
我々は、日頃から価格に、値付けをしています。
☆「○○にしては高い」「××にしては安い」と感じた体験
最近買ったもので、「これ、高すぎ!」とか「意外と安いな」と思ったものはありませんか? そんな感覚を参照点の視点で掘り下げてみます。
☆お店の雰囲気やサブスクって安く感じる?
お店の空間や体験が価格の印象に与える影響、サブスクリプションサービスの「安く感じる仕組み」を考えてみましょう。
☆得と損の感じ方、どう使い分ける?
得は小出しに積み上げる:小さな得を何回も感じるとうれしい。
損はまとめて済ます:損は一気に受けたほうが気が楽かも?
実生活で役立つコツもみんなで考えたいと思います。
毎回ゆるく開催していますので是非ご参加ください!飛び入り参加も大歓迎です!
皆さんで交流も深めましょう!
第4回:熊本にSuicaは不要?地域通貨の多様化と地域経済の行方
2025年2月25日(火)20:00~
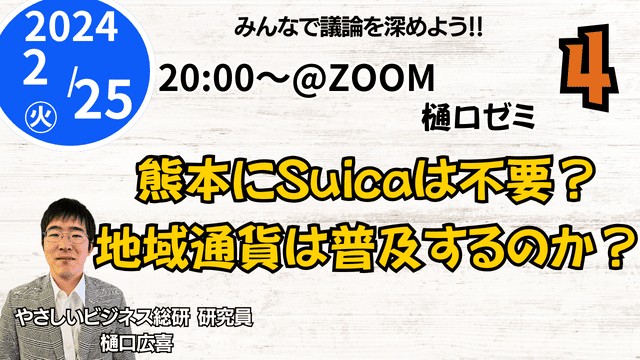
2月からリニューアル!! データサイエンスや経営学・経済学を学びながら、身近な話題を深掘りし、みんなで議論を深めていきませんか?
今回のテーマは―― 「熊本にSuicaは不要?地域通貨の多様化と地域経済の行方」
TSMCの新工場ラッシュで注目を集める熊本県。 しかし、県内では全国交通ICカード(SuicaやICOCAなど)が使えない地域があり、「導入コストが高すぎる」との理由が語られていますが、果たしてそれだけが真相でしょうか? 熊本は車社会ですが、TSMCの進出による交通渋滞の深刻化により、公共交通の需要は高まる一方と言われています。にもかかわらず、全国的なICカード対応ではなく、クレジットカード決済や、地域限定の「くまモン!Pay」推しが進んでいます。
背後に潜む「くまモン!Pay」の狙いとは? 地域経済活性化を目的とした独自戦略なのか?それとも、別の意図が隠されているのか? 地域通貨の乱立は、利便性を高めるのか、逆に不便を生むのか?そして、これらの地域通貨をどうすれば普及させ、住民や観光客にとって便利な存在にできるのか?皆さんと一緒に、現状を分析し、未来の可能性を議論しましょう!
やさビで学び、気軽に語り合う樋口ゼミに、ぜひご参加ください!